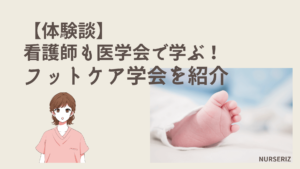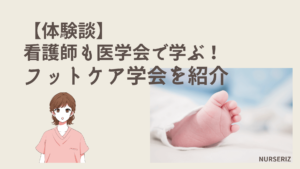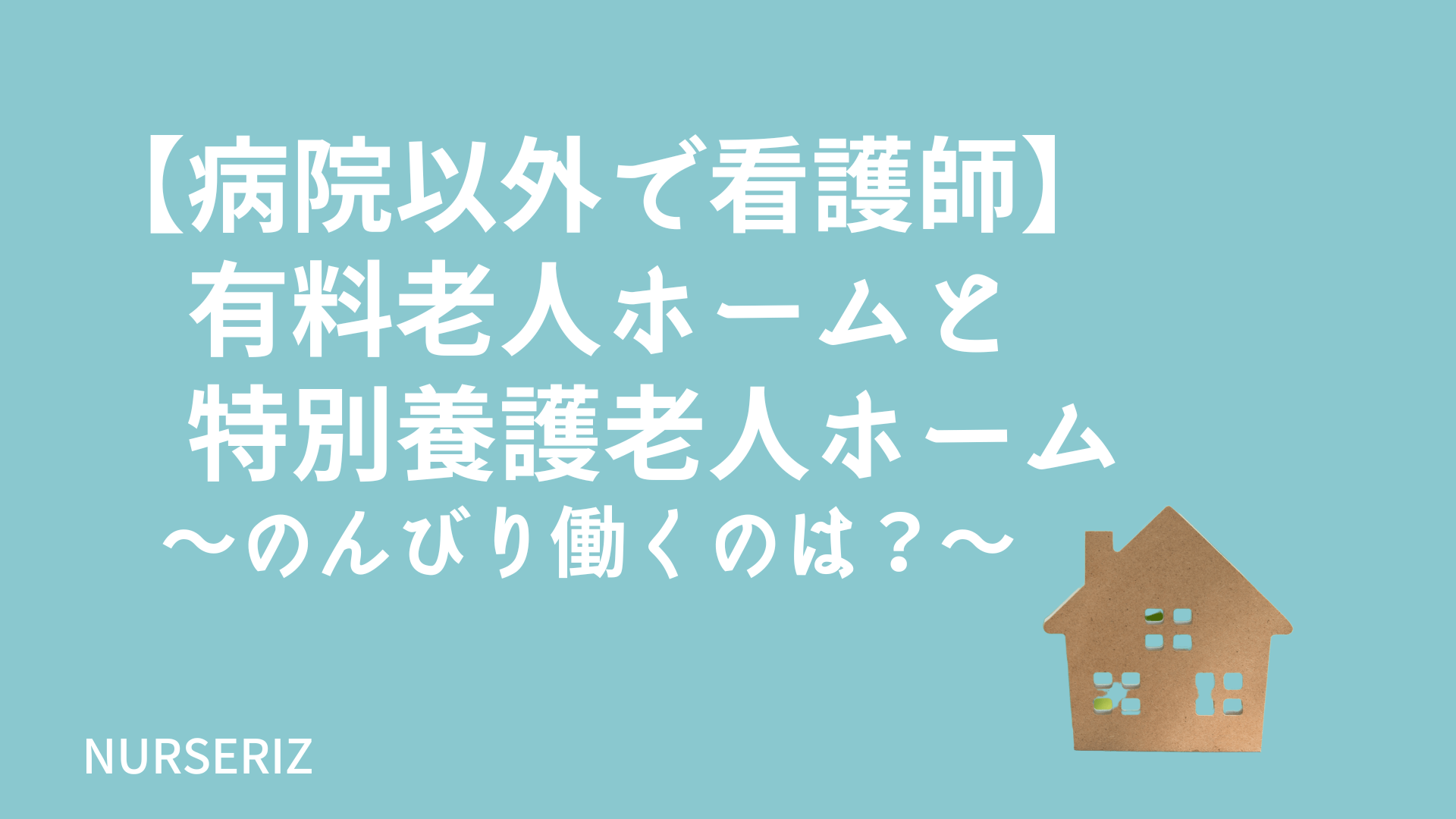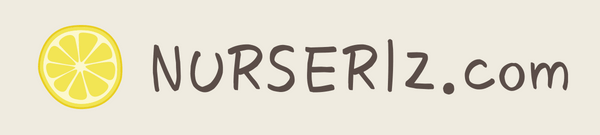日本フットケア・足病医学会の年次学術集会に参加したので、レポートします。
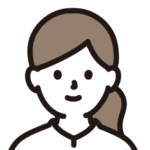
学会ってなんだか堅苦しそうなイメージ



そんなこと全然ないですよ
多くの看護師も在籍している、日本フットケア・足病医学会。
さまざまな研修会が開催されていますが、年に一回開催される年次学術集会は、もっとも大きなイベントです。
私は、2019年から毎年参加し、今回で4回目。
知識のブラッシュアップと学会資格の更新のために、毎年楽しみにしています。
今年はオンラインで参加したので、その様子をレポートします。
・日本フットケア・足病医学会に興味のある方
・フットケアの知識や技術を深めたい方
・看護師としてのスキルアップを検討している方
日本フットケア・足病医学会は足病医療・ケアを幅広く研究している学会


年次学術集会について紹介する前に、まずは学会について簡単にご説明します。
日本フットケア・足病医学会は、足病医療・ケアを幅広く研究している活発な学会です。
「足病」とは、下肢や足の障害(循環障害・神経障害)や感染、潰瘍などの病変を指します。
医師だけでなく、日々ケアをする看護師や介護職員、リハビリスタッフなど多職種で連携していく必要がある分野です。
そこで、日本フットケア・足病医学会は、2019年に(旧)日本フットケア学会と(旧)日本下肢救済・足病学会が合併して設立されました。
学会の認定制度がある
学会認定の資格は2つあります。一つは「フットケア指導士」、そしてもう一つは「学会認定士」です。



私はフットケア指導士を取得しています
認定資格1:フットケア指導士
医療や福祉の専門職員が、フットケアの専門知識と技術を身に付け、下肢の障害を予防・ケア・フォローすることで、患者やケア対象者のQOLを向上するために設立された資格です。
フットケア全般の優れた知識と技術を有する医療/福祉職者が認定されます。講習を受講後、試験に合格することで資格を取得できます。
フットケア指導士についてはこちらの記事に詳しく紹介しています。
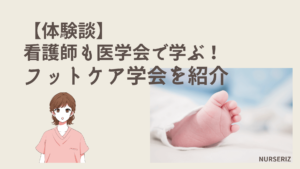
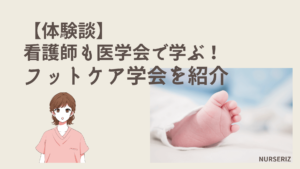
認定資格2:学会認定士
創傷治癒センターや下肢救済センターなどのほか、各フットケア外来におけるゲートキーパーとしての役割が期待される資格です。
認定師になるためには教育セミナーの受講が義務付けられており、下肢の解剖や創傷に対する専門知識が必要です。
下肢の解剖・血流・糖尿病を代表とする代表的疾患・下肢の創傷・フットケアやフットウェアなどをはじめとし、さまざまなセミナーを受講して必要な点数を獲得すると認定されます。
足病診療ガイドラインを制定している
2022年に「重症化予防のための足病診療ガイドライン」を出版しました。
足病の治療やケアに携わるすべてのスタッフが知識を共有して緊密に連携するための基礎としてまとめられた一冊です。



看護師にもわかりやすいガイドラインです
足病治療の指針となる68のクリニカル・クエスチョン(診療上の疑問)が提示されており、それに対する返答が提示されています。
内容を簡単に紹介すると…
・疫学・病態
・足病変の管理と治療
・再発・重症化予防
・歩行機能の確保
・集学的治療
・地域連携
このような内容が網羅されています!
足病についての診療・ケアについてエビデンスに基づいて詳しく紹介されているので、私自身、ケアの方向性に迷った時にはいつも参考にしています。
エビデンスと推奨度が紹介されているので、悩みを解決してくれる頼もしい一冊です。
多職種が参加することで幅広い知識が得られる学会
学会員の職種は多岐にわたります。
医師
看護師
薬剤師
理学療法士
技師装具士
健康運動指導士
介護福祉士



多職種が参加していることがわかります
医師の専門科も幅広く、整形外科・循環器内科・形成外科・皮膚科などさまざまです。
それぞれの専門性を持ちながら、互いに意見を出し合い尊重しあうという風潮が強い学会の雰囲気があります。
精力的に活動している看護師も多く、論文や研究発表からいつも刺激をもらっています。
先日の学術集会ですが、日本フットケア・足病医学会の会員は、約5,500人。そのうち約3,000人は看護職とのことです。
年次学術集会は、1年に1回行われる大規模な催し


フットケア・足病医学会では、毎年一回「年次学術集会」が開催されます。
この集会は、全国の学会員が一堂に会し、様々な専門性をもって研究結果を発表します。
年次学術集会と聞くと、なんだか難しそうなイメージがありますが、フットケア・足病医学会の集会は他とは一味違ったものになっていますので詳しくご紹介しますね。
2023年度の年次学術集会のホームページはこちらです。
今年の年次学術集会は沖縄・オンライン参加も可能
2023年度の開催地は沖縄県の『沖縄コンベンションセンター』でした。



沖縄まで行くのは大変そう
そんな方は、オンラインでの参加が可能です!
オンラインでは、当日だけでなくオンデマンド配信も視聴できます。
会場で参加した方で「もう一度視聴したい」「時間が重なってしまって聞けなかった講演を視聴したい」場合にも、オンデマンド配信を利用できます。
オンデマンドの配信期間は、学会当日~約1カ月となっているので、ゆっくりと聴講できるのも魅力です。
参加費用
参加費用は、職種により異なります。
職種
参加費用
医師(会員)
14,000円
医師・企業以外(会員)
12,000円
医師(非会員)
16,000円
医師・企業以外(非会員)
14,000円
企業
16,000円
研修医
5,000円
学部学生
無料



看護師は「医師以外」に該当するので12,000円です
参加登録を早めに行うと割引になる制度もあるので、早めの参加登録がおすすめです。
ちなみに、現地参加もオンライン参加も参加費用は同額になります。
学会の会員でなくても参加は可能
年次学術集会への参加は、日本フットケア・足病医学会の会員でなくても可能です。
非会員は参加費用が2,000円ほど割高になってしまいますが「興味はあるけれど、会員になろうか迷っている」といった方も参加できるようになっています。
年次学術集会に参加するデメリット
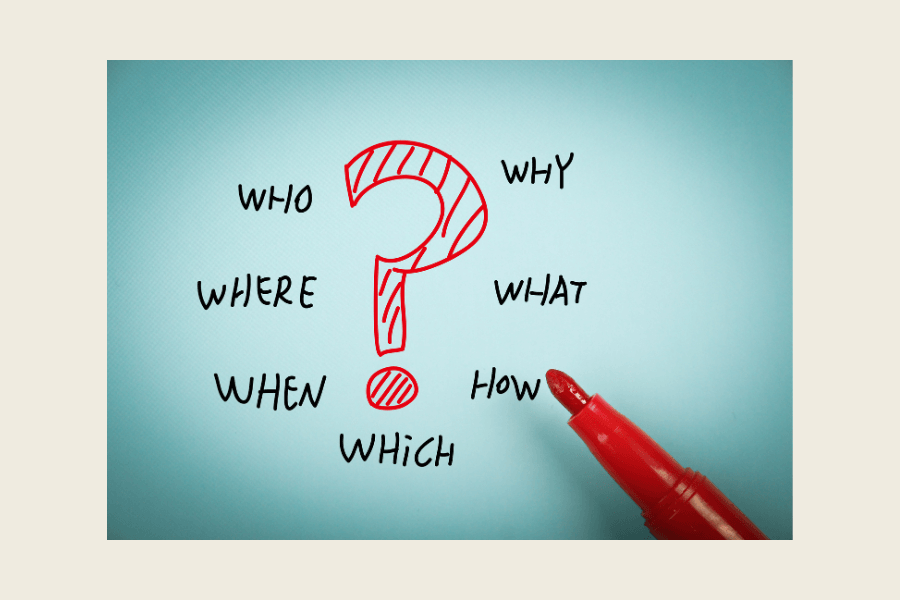
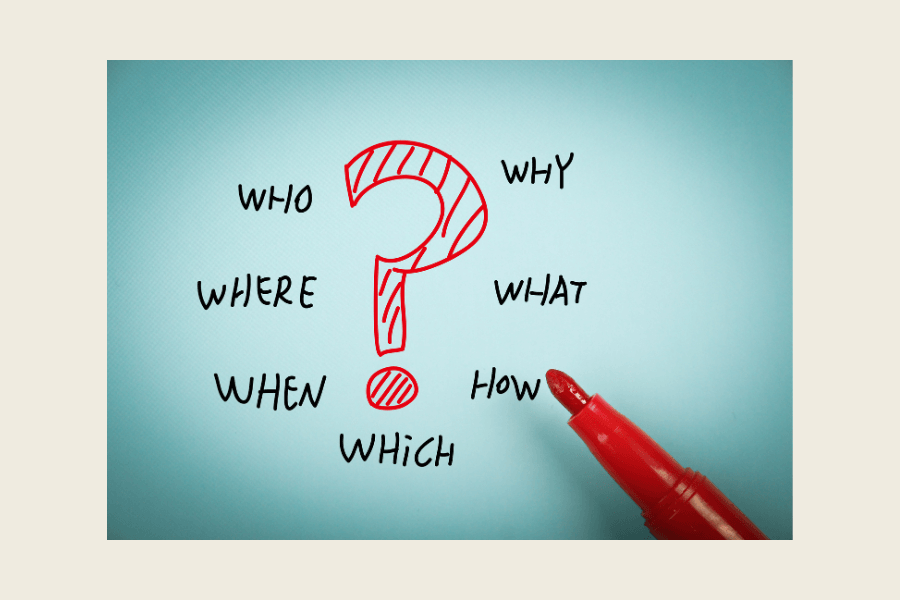
年次学術集会に参加するデメリットはあるのでしょうか。
現地とオンラインを含めて4回参加した経験をもとに、ご紹介します。
開催場所は日本全国にわたり遠征する手間がかかる
学術集会の開催場所は毎年異なります。
2021年度 横浜
2022年度 奈良
2023年度 沖縄
開催地まで実際に行くとなると、ホテルや交通機関の手配の手間や、移動時間がかかってしまいますね。
参加費用に加えて、開催地までの交通費・宿泊費が掛かる
前述した参加費用に加えて、交通費と宿泊費を合わせると、かなりの出費になることが予想されます。
とくに2023年度はクリスマスシーズンの沖縄での開催。
交通費と宿泊費で10万円を超えてしまいそうですね。
現地参加の場合には、時間と費用の面での負担が大きくなってしまいます。
年次学術集会に参加するメリット
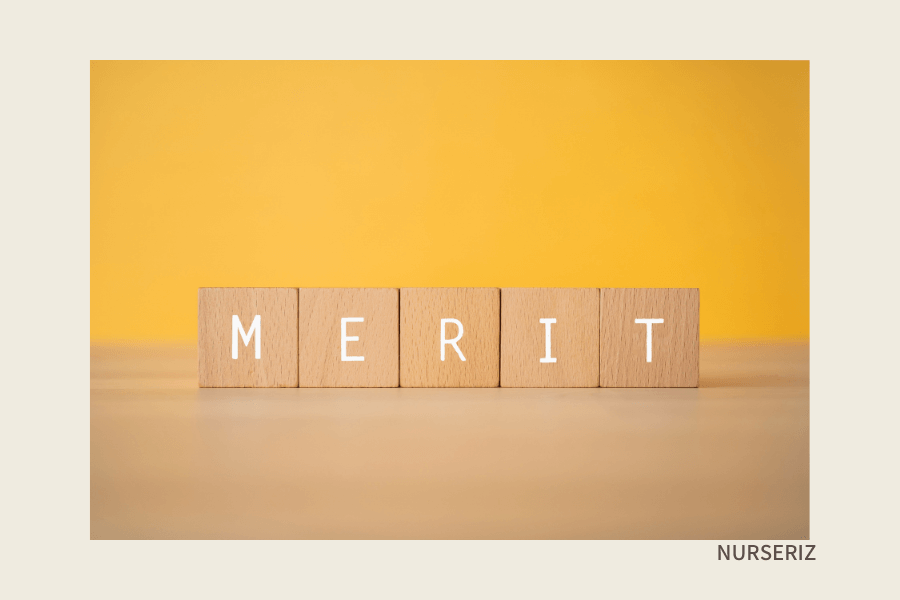
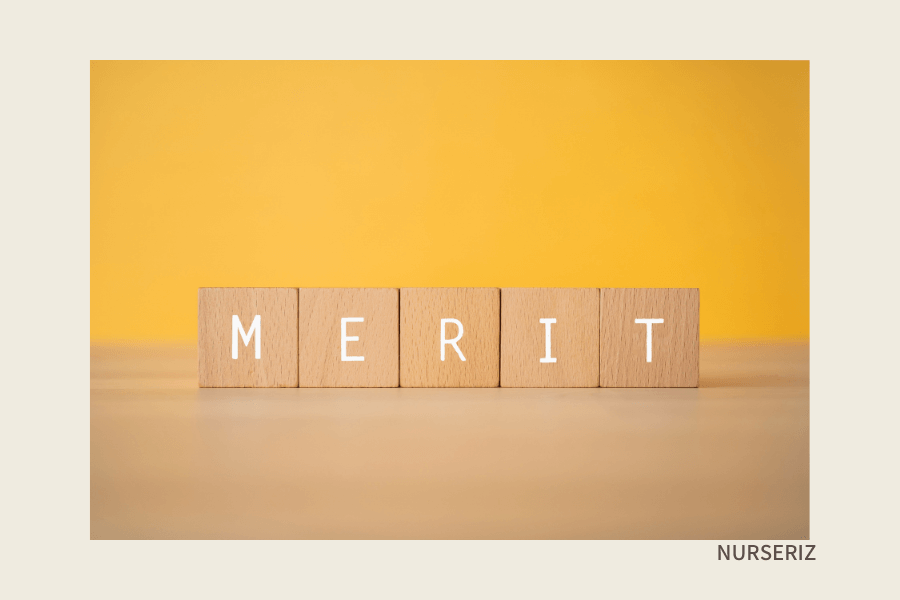
続いて、年次学術集会に参加して感じているメリットについてご紹介します。
最新の研究に触れられる
「こんな治療法があるんだ」「この薬剤はこんな効果があるのか」など、必ず新しい発見がありますよ。
また、フットケアと足病を熱心に研究している専門家の話を聞くと、自分のモチベーションアップにもつながります。
スタンダードな内容の教育講演も毎回行われるのでフットケアについて勉強し始めたばかりの方でも気軽に参加できます。
講演は多岐にわたる
多職種の視点を知れる
看護学会とは違った魅力がある日本フットケア・足病医学会。
講演やポスター発表を通して、多職種の視点を知ることができます。
普段、あまり連携することのない技師装具士や健康運動指導士の取り組みを聞く機会もあります。
看護師だけでは解決できないことを、他の職種であれば軽々とクリアしてしまうのかと感じる機会も多いです。
年次学術集会は、幅広い視点や多職種の技術を得られる貴重な機会と感じています。
交流会を通してフットケア仲間ができる
年次学術集会では、認定師・フットケア指導士交流会が開催されます。
交流会では、テーマに沿って座談会を行います。
全国から集まる多職種のフットケア仲間と交流するチャンスです。
私はあまり積極的な性格ではないのですが、交流会を通して同じ都道府県で働く看護師のフットケア仲間が出来ました。
研修の情報交換や、わからないことを相談できる関係になっています。
イベントが楽しい
年次学術集会では、さまざまな楽しめるイベントも企画されています。
学術的なセッションだけでなく、分野を超えて最新の足病医療を体験できるコーナーや、大物アーティストのイベントなども。
過去には、スタンプラリーなど開催されていました。
有名人の講演会も企画されています。
今回のイベントは…
・ポイントをためて「あし丸くんグッズ」をゲットしよう!
・免荷装具と義足の歩行を体験してみよう!
・ウォーキング講座
・メディカルファッションショー
今年度の学術集会で注目のテーマ


今年のテーマは「Challenge! 花ひらく未来へ」
日本には足病学や足病医が存在せず、欧米のような足病診療がありません。
そのため日本では、足に異常があってもどこを受診してよいか迷うことが珍しくありません。
そこで今回は、「足病必携マニュアル」を筆頭演題とし、適切な足病診療がどこにいても受けられるような体制になることを目指して開催されました。
演題を見てみると、「アセスメント~足はこう観る~」から始まり、「リウマチ足を救おう!~みんなでできること~」、「
意外と知らない脈管の知識」「足を支える栄養学」「みんなで知ろう免荷・補装具の基本」など、多職種の知識のすそ野を広げるようなものが目白押しです。
受講した演題
興味のある演題が目白押しですが、今回は筆頭演題の「足病必携マニュアル」の他に、以下の演題を受講しました。
・看護でここまでできる!足病医療
専門・認定看護師や特定行為研修修了者の活動に刺激をもらいました。
・形成外科医はこうやって傷を治す
形成外科医の外科的処置と外用薬のメソッドを学びたいと考え受講。
・再生医療で足を救え!
最新の再生医療を知り、治療をあきらめない姿勢の大切さを痛感しました。
・論文を書こう!~発表を論文にする方法~
論文執筆に興味があるので参考にしようと思います。
・米国と韓国に学ぼう!多職種連携チームでの足病治療
国外の足病治療や連携についての知見が広がりました。
学術集会は知識の更新とモチベーションアップに有効


年に一回の学術集会は、最新の知識を得る貴重な機会です。
全国から多職種の専門家が集まるので、モチベーションのアップにもつながります。
現地に行きたい気持ちを抑えつつ、今年はオンラインで参加しました。
オンデマンド配信はゆっくり自宅で見れるというメリットがあります。
でも、現地参加の楽しさには代えられないなぁと実感しました。
来年度は11月に神戸で開催予定です。
こちらは現地での参加を予定しています。いまから参加がとても楽しみです。
第5回 日本フットケア・足病医学会学術集会
2024年11月29日(金)~30日(土)
神戸国際会議場、神戸ポートピアホテル