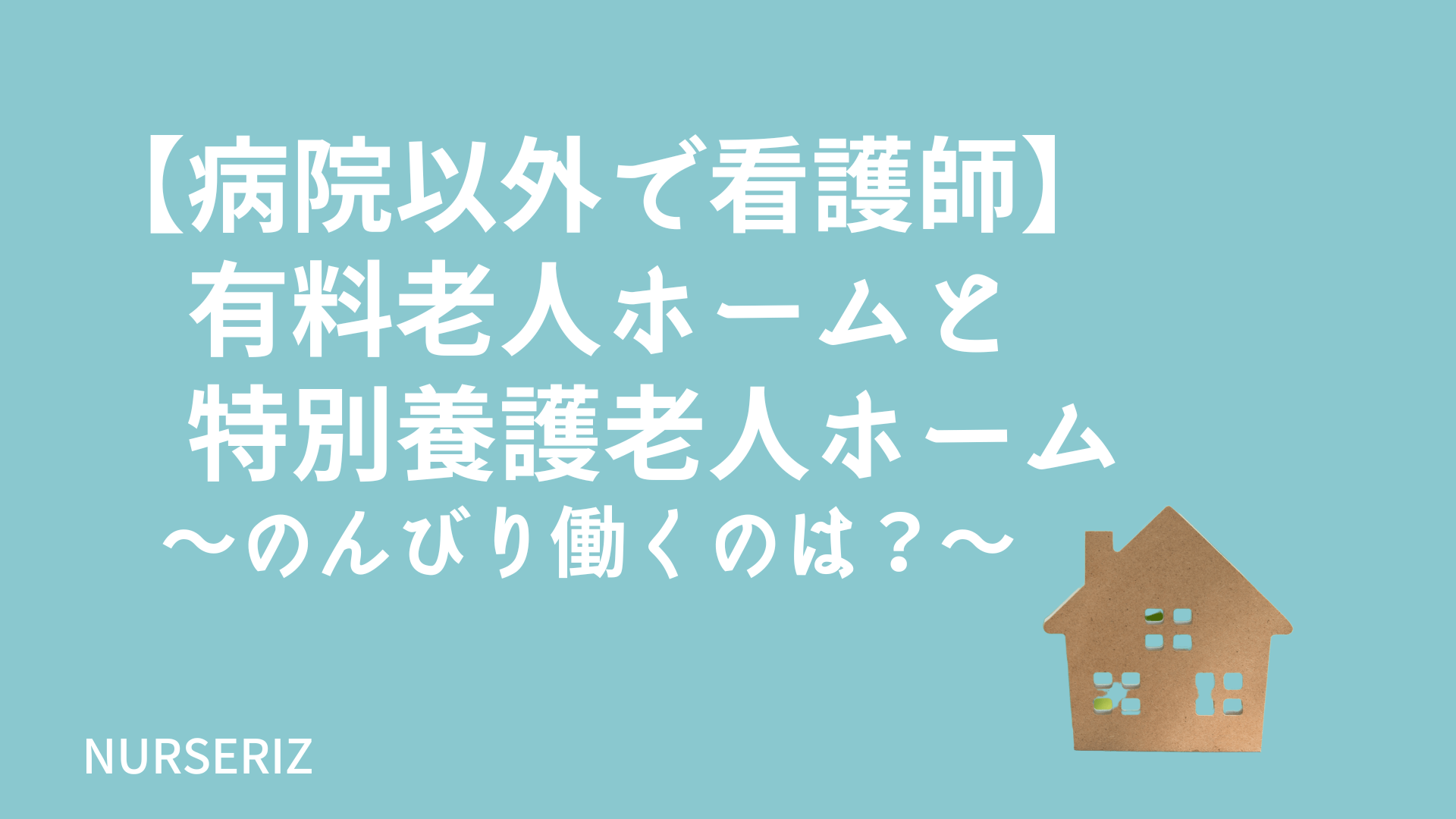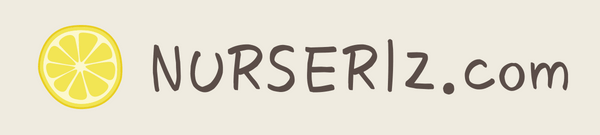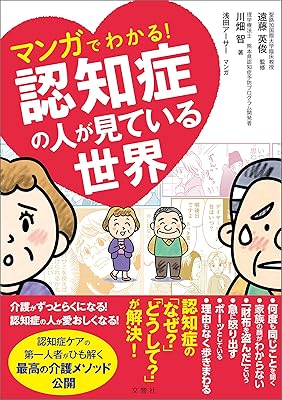・同じ話を繰り返す
・物をとられたと言う
・家族のことが、わからなくなってしまった
認知症の人のさまざまな言動に、周りの人が不安を感じてしまうことは珍しくありません。
2025年には、65歳以上の認知症患者数が約700万人まで増加するという国の試算があります。
参考:内閣府 高齢社会白書
高齢者の約5人に1人が認知症になると言われているのです。
決して他人事ではなく認知症と共生する社会がすぐそこまで来ています。
しかし、私たちは認知症についてしっかりと理解できているでしょうか。
日ごろから認知症ケアに携わっている看護師の筆者でも、接し方に迷うことがあります。
 RIZ
RIZ認知症を正しく理解できてる?



この声かけで良かったのかな?
もっと良い接し方があったのでは…
いつかは、自分自身や家族が認知症になるかもしれません。
すでに、認知症の家族を介護しているという方も少なくないでしょう。
この記事では、認知症のおすすめ本7選を紹介しています。
認知症への対応に不安や迷いを抱いている方にとって、きっと接し方のヒントになる本があるはずです。
ぜひ参考にしてみてください。






看護師・保健師免許取得。
国立病院(4年間)・私立大学病院(8年間)・行政保健師(1年間)を経験。
4回の転職を経て、現在はプライベートと仕事の両立ができる職場で働いています。
看護師が自分を消耗しすぎずに働ける「理想の職場」を模索中です。
1.マンガでわかる!認知症の人が見ている世界
多くの認知症の方と接してきた専門家が、不可解な行動の裏にある心理について詳しく紹介している本です。
同じ話を繰り返したり、理由もなく歩き回ったりする認知症の症状の裏には何があるのか。
マンガ形式でわかりやすく紹介されています。
認知症の人が感じていることや心の動きが詳しく描かれており、それぞれの症状に「なるほど」と納得できました。
この本のおすすめポイントは、一つひとつの症状ごとに対応方法が紹介されている点です。
「理解するだけで上手く対応できるようになる」のは、なかなか難しいのが認知症ケアの現状だと日々感じています。
この本には対応へのヒントがちりばめられているので、認知症の人が見えている世界を理解するだけでなく、どのように接したら良いかも分かるようになっています。
この本がおすすめの人
・認知症を理解して接し方を知りたい
・詳しく知りたいけれど活字でなくマンガで読みたい
2.認知症 世界の歩き方
デザイナーが表現した斬新な認知症の世界。
認知症とともに生きる世界では、いろいろなハプニングを体験することになります。
・人の顔が分からなくなる「顔無し族の村」
・行き先が分からなくなる「ミステリーバス」
・時計のリズムが変化する「トキシラズ宮殿」
・見えないものを想像できない「ホワイトアウト渓谷」
この本では、認知症の人が生きている世界を「異世界RPG」風に表現しています。
ユニークな表現が多く、楽しく読み進むことができます。
まるで旅行ガイドのように認知症の世界を見ることが出来る一冊です。
この本がおすすめの人
・認知症当事者の目線を知りたい
・専門用語ではなくイメージで認知症を捉えたい
3.ボケ日和―わが家に認知症がやって来た!どうする?どうなる?
認知症の進行を、日本の四季「春・夏・秋・冬」に分けて、そのとき何が起こるのか?どうすれば良いのか?をエッセイ形式で紹介しています。
認知症専門医である著者と多数の患者さんとの心温まるエピソードを読んでいると
人生100年時代、誰もが避けられない道
知っていればだいたいのことは何とかなる
本書のテーマが、しっくりくるようになるでしょう。
認知症は特別なことではなくある程度自然なことなのだと、優しく前向きな気持ちになれる一冊です。
認知症に対して、漠然と「ボケたら終わりだ」と不安に思っている方でも、上手に付き合っていく希望を持てるかもしれません。
この本がおすすめの人
・認知症に対する不安が強い
・初期症状から進行していく過程を知りたい
4.ボクはやっと認知症のことがわかった
医療や介護に関わる人であれば、知らない人はいないほど有名な長谷川医師が執筆した一冊です。
著者は長年、認知症診療の第一人者として活躍。
認知症の評価基準である「長谷川式スケール」の考案や、「痴呆」という呼び名の改称などにも尽力されました。
そんな認知症の権威である長谷川医師が、「認知症になってようやくわかったこと」を、当事者目線で綴っています。
さらに認知症の歴史や超高齢化社会を迎える日本の選択などの解説もあり、当事者の思いを理解することの重要性を再確認できる一冊です。
この本がおすすめの人
・当事者の思いだけでなく認知症の歴史や変遷も知りたい
・介護の仕事に携わっている
・認知症専門医の自伝に興味がある
5.消えていく家族の顔~現役ヘルパーが描く認知症患者の生活~
徘徊・せん妄・幻視・暴力・拒否・抑うつ…。
これらの症状の裏側に、当事者はどんな気持ちを抱えているのか。
アルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症・若年性認知症など、さまざまな当事者の「心」を明らかにしている本です。
現役ヘルパーが書いている本書ですが、介護職員目線ではなく、認知症の当事者目線で描かれています。
コミック形式なのでスラスラと読めますが、描写が繊細で感動的なシーンもある素敵な一冊です。
この本がおすすめの人
・認知症の症状に困っている
・介護の仕事に携わっている
・マンガ形式で読みたい
6.丹野智文 笑顔で生きる -認知症とともに-
若年性アルツハイマー型認知症当事者の丹野智文さんの体験談です。
39歳で診断された丹野さんは、不安や悩みを抱えながらも前向きな生き方を模索してきました。
社会の対応から感じた「生きづらさ」についても、正直に書かれています。
読み進めていくうちに、家族や会社の同僚、友人のサポートには思わず涙がこぼれました。
丹野さんが辛い時を乗り越え、認知症と共に笑顔で生きていける秘訣がわかり、前向きな気持ちになる一冊です。
この本がおすすめの人
・認知症当事者の声が聴きたい
・若年性アルツハイマー型認知症について知りたい
・家族会などのサポートを知りたい
7.認知症のわたしから、10代のあなたへ
43歳の時に若年性認知症の診断を受けた、さとうみきさんの書籍です。
ティーンエイジャーにも読みやすいよう平易な言葉で綴られていて、とても読みやすいです。
認知症と診断されてすぐには、家に閉じこもっていた佐藤さん。
しかしそこから、当事者や支援者との出会いを通して生活が変わっていきます。
子育て中の主婦さとうさんならではの、温かみのある文章が心に響く一冊です。
タイトルには「10代のあなたへ」とありますが、全世代の方に読んでいただきたいです。
認知症を一人で抱え込まずに、周りの人や家族と一緒に生活を切り開いていく強さを感じました。
この本がおすすめの人
・認知症当事者の声が聴きたい
・若年性認知症について知りたい
・家族で認知症について考えたい
まとめ|認知症を知るには専門書よりも当事者の声を聞くこと


数年後には、高齢者の5人に1人が認知症となると推計されている日本。
認知症と共に、あたりまえに生きる社会の実現のためには、まずは認知症について知ることが重要です。
NURSERIZは、認知症について知りたいと思い、さまざまな専門書を読んだり、研修に参加したりしてきました。
でも、最近は当事者の声を聞くことの重要性に気付きました。
認知症の方の見える世界を知ることで、自分の中での不安や戸惑いが減ってきていることを実感しています。
認知症をテーマとした本は、今回紹介したもの以外にも数多く出版されています。
ぜひ、色々な書籍を手に取ってみてください。